Oct,16,2012
私たちの赤裸々な日常をつづったチャリダー日記、レー・マナリロード編。
今回は、レー再出発から、ツォモリリを経由し、レー・マナリロードを走ってケーロンに至るまでの走行日記です。
なお、GoogleMap、標高プロファイル、距離一覧表、簡単なホテル情報をNotesにまとめてありますので、そちらも参照して下さい。
→Click Here!
| 2012.08.26 | Leh – Hemis Gompa | 44km | Campsite |
 重い腰をやっとの思いであげて出発。まずはシェイの旧王宮へ寄る。旧王宮そのものは特に印象に残らなかった。シェイを出ようとしたら、やけに多くの車が村外れの街道沿いに停まっているで何だろうと通りがかったおじさんに聞くと、今日はフェスティバルがあるという。よく耳を澄ましてみると太鼓の音が聞こえる。何かおもしろそうなことが起こるのかなと村に再び戻ってみると、さっきまで閑散としていた村の通りに人々がわらわらと集まってきていた。村人に聞いてみると昨日・今日が収穫祭らしい。白馬に乗ってやってきたシャーマンは村人たちから次々と酒を注がれ、馬から落ちそうになりながらも村人たちに神託を告げてまわっていた。今日を境にツァンパ(大麦)の収穫が始まるそうだ。 次はティクセゴンパ。今日はスタンプラリーのように観光地が並んでいる。ティクセゴンパはほとんどが改装されていて観光客も多かったので、ゴンパというよりは一大観光地に来た感じが強かったけれども、上階の小さなオールドライブラリーは古く雰囲気がよく、穏やかな顔をした観音菩薩像が素敵だった。 Karuで宿をとってチェムディゴンパ&ヘミスゴンパには空荷で行こうと予定していたのだけれども、Karuで適当な宿がみつからなかったので(恐らくトラック運転手が仮眠するような場所はある)、チェムディゴンパは諦めることにして、ヘミスゴンパにフル装備のまま向かった。街道沿いからほんの7kmだけ離れたところにあるヘミスゴンパなのだけれども、標高350mアップと意外に急坂で思いのほか苦戦した。ゴンパにキャンプサイトがあるということで、さぞかし雰囲気がいいのだろうと勝手に期待していたら、雰囲気のかけらもないキャンプサイトでがっかり。併設のレストランも高めだったので、わざわざヘミスゴンパでキャンプすることもないなと思う。ヘミスゴンパは異例の入場料100ルピーと高額でびっくり。プグタルゴンパではお布施を喜んで一人100ルピーを支払ったし、どこのゴンパでも必ずお布施を置いていくようにしているけれど、入場料として支払うとなんかしっくりこない。頑張って登ってきたという思いもあって期待も大きかったのもあったけど、ヘミスゴンパの外観も内観もパッとせずがっかり。(ようこ) |
|||
| 2012.08.27 | Hemis Gompa – Kiari | 80km | Camp |
 ヘミスのキャンプ場のレストランは高くて美味しくないので、クッキーをかじって次の町Upishiまで朝食は我慢することにした。昨日頑張って登ってきた道をあっという間に下り、さらにしばらくアップダウンを走ると分岐の町ウプシに到着。ウプシで朝食をモリモリ食べていると、売店のおばちゃんから「タルチョは自転車のフレームじゃなくてハンドル(もっと高い位置&風でちゃんとはためく場所)につけなさい」と注意される。同じ注意をレーでも受けたばかりなので、今度は真面目に聞くことにしてタルチョをハンドルにつけなおす。 ウプシで一旦レー・マナリロードを離れ、ツォモリリに向けて狭い谷間をひたすらインダス川沿いに上がっていく。ツォモリリ方面への道はチャリダーだとパーミット(入域許可証。レーで簡単に取得できる)を持っていても追い返されてしまうという噂もあったのだけど、ウプシのチェックポストはパーミットのチェックすらなく難なく通過できた。ウプシからの道が舗装路だったのはうれしい誤算だったけど、進んでも進んでも景色が全然変わないのでいまいち面白くない。 夕方遅く、Kiari村に到着。村というよりアーミーキャンプだったためテント泊はなかなか難しそうだったけど、もう時間も遅いし次の村まで走るのも大変そうだ。ダメもとで村の端っこにあった民家にテントを張らせてくれないか頼んでみたら、すんなりOKをもらって玄関先にテントを張れることになった。共同の井戸や共同トイレもすぐ近くにあってなかなか便利な場所に張らせてもらえた。家のおばあちゃんはチャイを出してくれたり、突風が吹きだしたらテントの張り網を机やガス缶に縛り付けてくれたりと、突然の訪問者にもかかわらずテキパキと世話を焼いてくれる。ラダックにはてきぱきとよく働く女性が多い。(ひろ) |
|||
| 2012.08.28 | Kiari – Sumdo | 58km | Camp |
 朝起きると、まるでタイミングを見計らっていたかのような素早さでおばあちゃんが温かいチャイを持ってきてくれた。甘くて温かいチャイが沁みる。去り際にチャイのお礼ほどにしかならないけれども幾ばくかの礼を渡そうとしたら、おばあちゃんはぶんぶんと首を振って受け取らず、「ツォモリリからの帰りもまた泊りに来なさい」って少し恥ずかしそうに優しく笑ってくれた。 今日の道も相変わらず単調でつまらない。Chumathangはトラックストップでレストランが2、3軒あったので、ここで遅い朝食を取る。ついでにお昼用にチャパティとオムレツも頼んでおく。レストランのおばちゃんにタッパーを渡すと、チャパティにオムレツを包んでサンドイッチ風にしてきれいにタッパーに詰めてくれた。こういうオーダーは多いのか、ちゃんと心得てる。この村には温泉が湧くようで、ホテルやキャンプ場もあった。 Mahe Bridgeのチェックポストを過ぎると景色が変化してきて、絶景とまではいかないけれど、どんどん素敵な風景になってきた。嬉しいチャパティ&オムレツランチを取った後、すこぶる天気が悪くなってきた。砂嵐に向かい風にヒョウ。最近夕方になると天気が荒れる。せっかく景色が良くなってきたのにまわりはほとんど何も見えなくなってしまって残念だ。 今日の宿泊予定地はスムド(プガ・スムド)、もっとも宿泊予定地といっても宿はない。村でテントを張らせてもらう予定に勝手にしているだけのことだ。あっけなく村の中心にある大きなマニ車の横に張ってよいよと了解を得る。村の中心なだけに人々がマニ車を回しに来たふりをしながらどんどん集まってきた。「あれ、女性たちがチベットのエプロンをしているな」と思ったら、後でこの村はチベット難民の村だと分かる。挨拶を「ジュレー」(ラダック語のこんにちは)から「タシデレー」(チベット語のこんにちは)に変えるとみんな嬉し恥ずかしそうに「タシデレー」とにこにこ返してくれる。女の学校の先生2人がお茶に誘ってくれたので、早速先生のおうちにお邪魔する。お菓子にお茶にといただきながらいろいろとこのチベット難民村のことを聞くことができた。今日はテントを張ってしまったけど、ツォモリリから帰ってきたら学校に泊ったらいいわよと言ってくれる。それは楽しみになってきたぞ。(ようこ) |
|||
| 2012.08.29 | Sumdo – Korzok(Tso Moriri) | 40km | Homestay |
 スムドを出るとすぐ峠道が始まる。早朝は天気が良かったのにすぐに曇り空になって、そのうちヒョウまで降りだした。途中、手でつまめる距離にナキウサギを発見。岩影に隠れようとしているのに隠れきれず、丸見えのままじっと固まっているのが可愛い。北海道の山ではよく鳴き声を聞いていたけど、こんな至近距離で見るのは初めてだ。 Namshang峠を登り切ると小さな湖Kiagar Tsoが見えてくる。周りに人工物が何もないワイルドそのものの風景を、きれいな舗装路の下り道を降りながら堪能できるのは素晴らしい贅沢だ。でもまあよく考えれてみれば舗装路ほど人工的なものはない訳で、「立派な舗装路だけあって他に人工物がないのがいい」なんていう自分の勝手な言い分には苦笑いしてしまう。 ツォモリリ湖畔の町コルゾックまで残り20kmというところで舗装路が終わり、あとは砂や石だらけの走りにくい未舗装路が続いていた。天気もますます悪くなってきて、コルゾックに到着して昼飯を食べている頃には本降りになってきた。せっかくのツォモリリも雨では全然きれいに見えないし、町の雰囲気はあまり好きになれないし、テンションは下がる一方だ。 夕方になるとようやく青空が見えてきて、ツォモリリもキラキラと湖面が輝きだした。対岸の山肌もカラフルで素敵な風景だったけど、まあツォモリリ自体は1泊もすれば十分かなという感じだ。(ひろ) |
|||
| 2012.08.30 | Korzok – Sumdo | 40km | School |
 観光地の食堂は高いとはいえ、うすっぺらい紙切れのようなチャパティが一枚10ルピーもして驚いた。昼用に二人で10枚オーダーしたものの、こんなに薄かったら足りないよなぁきっと。昨日の悪路に戻るのはブルーだったけど、すでに悪路と分かっていたので、いざ走ってみるとそれほど辛くはなかった。今日はいい天気でツォモリリ湖、キアギャル湖ともに碧くて素晴らしい。お昼ごはんはキアギャル湖を二人占めしてピクニック。チャパティ&オムレツにツナ缶までプラスした豪華なランチに二人ともニンマリ。 お昼後は少しだけ登って、後は快適な舗装路の下り。途中、昨日は結構な水量で流れていた川が今日はすっかりと枯れてしまっていたのには驚いた。今日は温かいし水浴びでもしようかと思っていたのにな。でもだいぶ下ったところに別の小川を発見したので、そこで水浴びすることに。太陽が隠れてしまったので寒いかなと緊張して川に入ってみると、水がほんのり生温かい。この標高でこの水温ということは温泉水がまざっているのかもしれない。数キロ離れたところに温泉があるからその影響なのかな。シャンプーして、ジャブジャブと体も洗って、ついでに洗濯もしてご機嫌。やっぱり綺麗になるって嬉しい。少し離れたところから羊飼いの女の子たちが私たちの行水を珍しいものでも見るかのようにのぞき見してる。女性たちだし、ま、いっか。 綺麗になって堂々とスムドの学校へ向かったら、村の入り口で学校の先生ヤンゾムがぼーっと佇んでいた。どうやら今日は1カ月に3便あるレー・ツォモリリ間のバスが通過する日で、レーから荷物が届くのを待っているようだ。届いた荷物にはりんごや梨などのフルーツが入っていて、大事なものなのにヤンゾンは惜しみなく私たちに果物を渡してくれる。大事なものなのだからそんなにいただけないと断ると、「何いってんの食べなさいよー、美味しいわよー。」って明るく突き返される。 彼女だって私たちがあと数日もすればいつでも野菜やフルーツが食べられるところへ行くことを知っているのに、そんなことはお構いなしで貴重なものを分けてくれる。その心の広さに感心する。ぜひとも真似できるようにならなければなと思う。(ようこ) |
|||
| 2012.08.31 | Sumdo | 0km | School |
 朝食のティモ(蒸しパン)が美味しくて朝からおなかいっぱいだ。授業開始前にヤンゾンが学校内を案内してくれてから、先生や子供たちに別れを告げていざ出発。ところが走りだしてすぐにようこが体調不良を訴え始めた。頭が痛くて息が切れるというので高山病が心配だ。今日はこれから5000m近い峠を越える予定だったので、ここは大事をとって10kmほど走った地点でスムドに引き返すことにした。すごすごとスムドの学校に戻ると、みんな驚きながらも快く受け入れてくれた。学校のゲストルームも小ざっぱりと気持ちがいいし、この村に縁があったのだと思って、今日は一日のんびり休憩させてもらうことにする。 合計3日目の滞在となったので、子供たちも少しずつ慣れてきて人懐っこい笑顔を見せてくれるようになった。ちょっとシャイな感じやはにかんだような笑い方とかが日本人っぽくてとても親しみがわく。昼食はライス&カリフラワーの煮込み。野菜は月に1回トラックでレー方面から運ばれてくる事になっていて、ちょうど昨日届いたばかりだそうだ。月末になると野菜の備蓄が尽きて米&豆の食事が続くというからなかなか大変だ。今日はデザートにフルーツ(洋ナシ)まで出てきたので子供たちはとてもはしゃいでいた。 午後は川に洗濯に行ったり、子供たちと遊んだり、ヤンゾンにお茶をごちそうになったりしてあっという間に過ぎていった。おかげで心も体もリフレッシュ、ついでにチベット難民村で素晴らしい体験までさせてもらえた。ようこの体調も落ち着いたようだし、けがの功名ってやつかな。(ひろ) |
|||
| 2012.09.01 | Sumdo – Pongunagu(Tso Kar) | 50km | Campsite |
 今日はすっかり調子がいい。昨晩はひろの調子が悪くなって、今度はひろがダウンかと心配したけど、どうやら大丈夫そうだ。標高が高いところでは安易に具合も悪くなれない。 今朝はなんだか冬のように寒い上に風も強い。今日の峠は標高約5000m。峠の上は大丈夫かしら。昨日引き返したポイントまでは調子よくたどり着いた。が、そこからの未舗装路の状態の悪いこと。調子が万全ではなかったのもあったけど、峠の前半はかなり自転車を押して歩いた。100m進むたびにゼーゼーハァハァと大げさに息しては休憩する。こんなに押した峠はこの4年でも初めてだったと思う。峠のタルチョがはためいているのが見えたときは涙がほろりと出た。チベット圏の峠ってやっぱり素敵だ。特にこの峠はタルチョが大量にはためいていて、これぞチベットの峠といえる立派なものだった。マニ石が立派に積まれていて風除けになっているのと、やっとの思いで着いたということもあって、お祝いにここでインスタントラーメンを作ってお昼にすることに。ぬけるような碧い空のもとでのラーメンは美味しかった! 下りも相変わらずの悪路に苦戦する。下りなのに全然楽じゃないよねとブゥブゥ文句を垂れながら走っていたら、予期せぬところから突然美しい舗装路が始まっていて感激。気まぐれ的に現れた舗装路、最初はいつ消えるのかとビクビクしながら走ったけど、無事に大きめの村まで到着。この先も舗装路が続くことが見込まれたのでひとまず安心だ。 自転車をチャイ屋に置いて村の高台にあるゴンパまで上がる。結構急な坂をひいこら登っていったのにゴンパに行くと坊主がいない。坂の始まるところで坊主がコンビニに集まるヤンキーのごとくたむろしていたので、「これからゴンパに行くけど、上には寺の鍵を開けてくれるお坊さんはいるか?」と聞いて「いるから大丈夫。」という返事をもらっていたのにだ。「こらー、坊主め!」と登ってきた方向を睨むが、もうその坊主たちはどこへやら。結局諦めて下ることに。下っていたら小さな嵐がやってくるのが見えたのでチャイ屋で小休憩。ラダック地方では何十キロ先まで遮るものがないことも多いから、嵐がどこで起こっているかが見えておもしろい。右を見たら青空、左の奥の方を見ると鉛筆で乱暴に塗り絵したかのようなグチャグチャモヤモヤした部分があったりする。 今日はツォ・カル入り口のキャンプサイトで泊る。ふわふわの芝生の横に小さな小川が流れている、こじんまりしていたけど心地のよいサイト。テント食堂はかわいいオジサンが切り盛りしていて、英語が通じないのだけどジェスチャーで要件を伝えると、いつもにこにこしながら「ニャーニャー」と答えてくれる(と言っている様に聞こえる)のがものすごく可愛いおじさんで、一日の疲れもすっかり忘れてほっこりだ。(ようこ) |
|||
| 2012.09.02 | Pongunagu – On the way | 79km | Camp |
 ツォ・カルのキャンプサイトはメインロードから少し離れた場所にあるのだけど、メインロードにどうやって戻っていいのかいまいち分からず、朝から無駄に未舗装路を走ることになった。途中で無理やりメインロードに出たのだけど、あとで地図を見ながら思い返してみればそのまま未舗装路を走り続けていたら大幅にショートカットできた気がする。 レー・マナリロードに合流したものの、合流地点近辺はあいにく工事中。せっかくハイウェイに戻ったのにコルゲーションだらけのデコボコ未舗装路が続く。しかもサンサンと太陽が降り注いだかと思えば、一瞬で空が真っ暗になって雨やヒョウが降り始めたりする変な天気。その都度レインウェアを脱いだり着たりしないといけないのが面倒くさい。しばらく続いた工事区間が終わると、ローラーブレードでもできそうな出来立てほやほやの快適舗装路が登場。やっぱり舗装路は快適だ。その後は300mほど下ってPangに到着。 Pangはテントレストランが10軒くらい並ぶトラックストップのような場所。適当に入ったレストランのターリー(定食)は微妙な味でしょんぼり。しかも向かいのレストランにお菓子を買いに行ったらそっちはインド人で賑わっていて、みんなとてもうまそうなターリーを食べていたのでさらにしょんぼり。再出発の間際、仏画修復の勉強に来たという日本人大学生の団体が車からぞろぞろ降りてきた。アシスタントの女性は親しく話しかけてくれたのだけど、学生たちは完全に僕らを無視。スタディーツアーとかNGO関係の人たちって、欧米人に対しては満面の笑みで挨拶するのに、僕ら日本人バックパッカーのことは完全に無視する傾向にある気がする。そんなに僕らって怪しげな雰囲気を醸し出しているんだろうかと、少しへこむ。 Pangから先は約600mアップの峠道だ。天気が悪くて寒いし、道も悪いし、なかなか大変な峠だった。Lachulung La峠の標高は約5080m。自転車で越える5000m超の峠は、今回の旅では何気に初めてだ。峠からの眺めは素晴らしかったし、下り道も美しい景色が続いたのだけど、もう夕暮れ近くの太陽が隠れてしまった時間だったので寒くてしょうがない。ガチガチ震えながら峠を下り切り、次のNakeela La峠が始まるちょうど谷間に1軒だけチベット人経営のダーバがあったので、今日はそこで終了することにした。ダーバの横にテントを張らせてもらうと、すぐに雨が降り始めて、結局そのまま明け方まで降り続いた。(ひろ) |
|||
| 2012.09.03 | On the way – Bharatpur | 68km | Dhaba |
 朝起きると周りの山々が真っ白に雪化粧していた。青空と眩しい白のコンビネーションが美しい。朝一番から峠だったけれど、雪景色のおかげで楽しみながら登れた。峠の下り道も綺麗で十分すぎるぐらいに美しいのに、それでも最近きれいな風景を見続けているせいか、息を呑むほど美しいというほどではないなと思ってしまう。贅沢なことだ。九十九折りの道をのんびり下っていると、下から登ってくるチャリダーが何人も見えた。ちまちまとでも確実に前に進んでいる姿は微笑ましいなぁと眺めていたら先頭の人がやってきて日本人だということが分かった。大学生のグループ(サークル?)でスピティバレーとレー・マナリロードを走りに来たという。大学生でこんな素晴らしいところを走ろうと選んだことが素敵。この周辺ではやたらインド人の自転車一日ツアー客をよく見かけた。普通こういう自転車ツアーはダウンヒルを楽しむのがメインだと思うのだけど、インドではよく峠を登ってくる自転車ツアーを見かける。インド人は登りが好きなのか?意外と根性がある人たちなのかもしれない。 サルチュで昼休憩。サルチュはトタンの掘立小屋がたち並ぶ醜いトラックストップだったけど、ネパール人経営の食堂のターリーは、店のしょぼいみかけとは裏腹にとても美味しかった。サルチュの少し手前くらいから強くなってきた向かい風は、休憩後どんどん強くなってきた。ひろと隊列を組み、2kmごとに前後を交代して走る。風を直接体に受けないと疲れ方も違うので、風が真正面から来る時は結構効果がある走り方だと思う。10回ほど交代したくらいから風が弱まってくれた。 Keylong salaiからBharatphurまでの道はかなり景色がよかった。青空と彩り豊かな岩山はいつ見ても惚れ惚れするコンビネーション。Bharatphurではテントを張らせてもらおうと思っていたのだけれども、強烈な風が吹いているし、テントを張れる適切な場所が見つからなかったので、結局ダーバ(食堂兼宿泊場)で泊ることになった。石を積み上げた壁と分厚ビニールシートを屋根にした建物は見かけは立派なのだけど、隙間風だらけでかなり寒い。寝袋カバーまで取り出して、完全防備で床に着く。床に着くっていってもレストランに雑魚寝なのだけど。寝付いたときは私たち2人だけだったのだけど、夜中に起きてみるとゴロゴロと転がっている人々が15人くらい、レストランはすっかり満員になっていた。15人も寝ていた割には風の音とネズミが走り回る音しかしないほど静かだった。でも朝5時ともなるとみんな起きだしてガヤガヤうるさい。朝早い時間だから静かにしゃべるとかバタバタ動かないとかそういう気遣いはゼロ。日が出ないと寒いから起きたくなかったけど、やむなく起きざるを得なかった。(ようこ) |
|||
| 2012.09.04 | Bharatpur – Keylong | 73km | Hotel |
 今日は標高4900mのBaralacha La峠の続きを攻めるところから始まる。朝から上り坂って結構つらい。この峠はどこが頂上なのかいまいち分かりにくいし、相変わらず天気も悪いしで残念な感じだった。下り道の途中には聖なる湖Suraj Talがあるのだけど、そこも天気が悪いせいでボチボチ。湖は晴れてナンボなのだ。きっと晴れたら美しい湖面の色がみられたに違いないと思うと残念だ。それにしても寒い。標高4900mから3600mまで一気に下り続けるのだけど、途中あまりの寒さに手足の指先の感覚がなくなってきたので、たまらずダーバでチャイ休憩をする。こういう時は温かい飲み物が本当にありがたい。一息ついてさらに下り続けると、Patseoあたりからようやく太陽が出てきて暖かくなってきた。気がつけば周囲は緑に囲まれていて、なんだかネパールの田舎のような風景になってきた。 Darcha村で昼食休憩をした後は、Keylongまで小さなアップダウンが続く。間近に氷河が見えたりして気持ちのいい風景だ。日本人っぽい顔をしたシャイなチベット系が多かったラダック地方と違って、この辺りでは穏やかで明るい笑顔のネパリ・インド系の人たちが増えてきた。 Keylongは期待していたほど大きな街ではなくて、一つの街道にホテルや食堂が数軒並んでいる程度の町だ。それでもビールは冷えているし、ネットカフェはあるし、商店には欲しいものが一応そろっているし、周りの景色はいいし、ホッと一息つくには十分の町だ。夕食に宿併設のレストランで久しぶりにチキンを食べてみたのけど、全然美味しく感じられない。すっかりベジタリアンになってきたか?きっとチキンのクオリティが低いだけなのだろうけど、こんなんだったらもう肉は食べなくてもいいやーと思ってしまう自分に驚く。明日、明後日はこの街でゆっくり休憩だ。(ひろ) |
|||
yokoandhiro | Diary, Ladakh & Zanskar

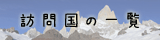
 RSS 2.0
RSS 2.0